| 1998年(平成10年)6月20日(旬刊) | No.43 |

|
|
連載小説 ヒマラヤの虹(14) 峰森友人 作
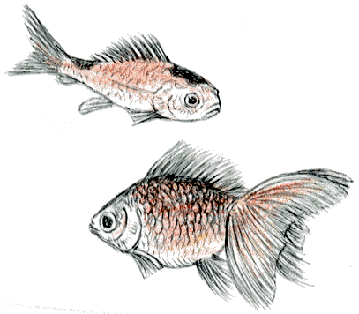
肌を刺す寒気をずっと我慢していた慶太は、ロキシーの生み出す熱で落ち着きを取り戻した。黒い山並みを覆う空は大小無数のきらめく水晶の粒でいっぱいである。その一つ一つがお互いにぶつかり合い、鈴の音のような透き通った響きをたてているような感じがした。いくつかの山を隔てたヒマラヤ山中のどこかで、百合もまた今この空を眺めているに違いない。百合はどのような姿で何を思っているのだろうか。ロキシーを手に星空に見入っていた慶太は、料理し終わったダールバートを持ってインディラが後ろに立っているのにまったく気付かなかった。 食事の後片付けが終わると、インディラは外は寒いからと、自分たちの部屋に慶太を招き入れた。六畳程の広さの細長い部屋の一番奥は台所で、いくつかのステンレスの食器が並べられている。土のかまどもついている。しかしインディラたちはこれを使っていない。木で出来た粗末な小さなベッドが一つ、この上でインディラとビジャヤの二人は寝袋を並べて一緒に寝る。ベッドの下は彼女たちのたんす代わりで、衣類や公衆衛生の通信教育の材料など個人の大事な物をすべてここに保管している。ベッドのまわりは土間。そのわずかな空間が彼女たちの居間である。二人の若い女性にとって、一部屋の空間が生活のすべてを行う神聖な場所であった。 インディラによると、百合らしい女性の加わった視察団が来たのは十二月初めだった。ドルフェルディ村と隣のフィルフィレ村の二ヵ所を二日間かけて視察した。村の女の日常生活がどのようなものか、何人かの主婦や十代の娘を中心に、克明な聞き取り調査が行われ、実際の労働の様子も見て回った。一行は全部で十人、カトマンズのネパール赤十字本部と国連事務所の女性問題担当者が案内して来た。外国人は、ノルウエー国際開発庁から二人、国際赤十字から一人だったが、その国際赤十字の専門家が日本人で、その通訳兼エスコートをしていたのが、インディラの前にこの地域でボランティアをしていたトリジャという女性だった。 一行は村の何軒かの農家に分宿した。トリジャも以前はインディラの部屋を基地にしていたことから、日本人研究者と一緒にこの家に泊まった。 「トリジャは私の部屋、日本人は二階のあなたの部屋」 少々たどたどしいが、それでも意味は十分分かるインディラの話しを聞いていた慶太は「あなたの部屋」という言葉で胸に熱いものを感じた。その日本人女性が百合だとまだ断定することは出来ない。しかし百合らしい女性が今晩自分が寝るその同じベッドで二週間前に寝た。その女性の、いや多分百合の香りがその粗末なベッドにまだ残されているはずである。 「その研究者はどんな感じの人だった?」 「太くない背の高い人。私の仕事のことや、ここのお母さんの朝起きてから夜寝るまでの生活のこと、詳しく聞いた。その人、小さな機械を持っていて・・・」 「機械?」 「そう、あの、あ、テープレコーダー。トリジャがここのお母さんから、私、歌上手だと聞いて、それでその人が私に歌えと言うので歌うと、それをテープレコーダーに入れた。まだ歌えるかと聞いたので、もう一つ別なのを歌った」 「その人はいまどこにいるか知ってる?」 「分からない。でもトリジャに聞けば、分かる」 「トリジャはどこにいるの?」 「分からない。ときどきゴルカの家に帰ると言っていた」 「それで、その日本人研究者は何という名前だった?」 インディラはちょっと首をかしげて、考える様子をした。部屋の中の暗闇の中でも、インディラの目は光っていた。インディラは思い出せなかった。 トリジャのゴルカの家のことは、ポカラの赤十字事務所で多分分かるだろう。三年前まで、その事務所の管理下で仕事をしていたのである。百合らしい女性が国際赤十字の専門家として来た。これは初めての情報である。ノルウエーよりもまず国際赤十字に当たる必要がありそうだ。 慶太は午前四時前、地鳴りのような音で目が覚めた。下から響いてくるその音をたどっていくと、物置小屋で家主とまだ幼い娘がコドを石臼でひいていた。鶏が鳴き、山の端が白み、水牛が大きなあくびのような声を出したのはそれからずっと後のことだった。 朝インディラは、予定を早めてプログラム・オフィサーに報告に行くことにしたので、途中二、三の農家を回りながら、一緒に山を下りると言った。二十一歳のインディラは華やかなピンク、十九歳のビジャヤは薄緑のクルタクロワールで、明らかにおしゃれをしていた。高校を出た後仕事を続ける二人は未婚だった。教育程度が高くなればなるほど、結婚時期は遅くなり、子供の数が少なくなるのは必然と言えた。 インディラとビジャヤが農家に寄って聞き取り調査をしながら山道を下る後ろ姿を見て、慶太はふと、百合とトリジャの姿を重ねてみた。たった二人で、出会う人のいない山中を村から村へ歩いて、百合は何を見つけようとしているのだろうか。百合の手紙には、「野生的な体験」をすると書いてあった。テレビ・ディレクターという時代の最先端にあった知的できゃしゃな肉体の女性が、果たしてトイレも水も不自由なヒマラヤの野生的な生活に耐えていられるのだろうか。慶太の前を行く軽い足取りのインディラが、いつのまにか石ころに足を取られてよろめいている百合の姿に変わった。
このページについてのお問い合わせは次の宛先までお願いします。 |