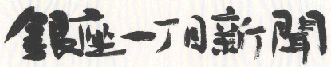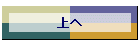

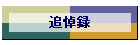
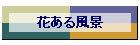

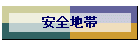
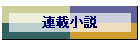
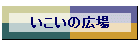
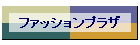
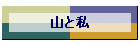
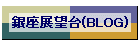
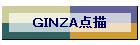
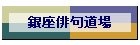
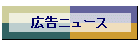
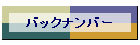
| |
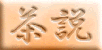
世代を超えて語り継ぐべき
戦争文学
 牧念人 悠々
牧念人 悠々

8月6日は「広島原爆忌」、9日は「長崎原爆忌」である。私のブログ「銀座展望台」に次のように書いた(7月16日・木曜日)。
『広島生まれの作家・竹西寛子さんに「広島が言わせる言葉がある」というエッセイーがある。
広島での被爆体験を初めて公表したデザイナー三宅一生さん(71)がオバマ大統領に対して8月6日に広島へ来訪するよう求めて「ニューヨークタイムス」に寄稿した。その中に次のような言葉がある。
「日系アメリカ人イサム・ノグチがデザインした広島市の平和大橋をオバマ大統領が渡る光景は核兵器の脅威のない世界を創造する現実的で象徴的な一歩になる」
まさに広島が言わせた言葉である。
三宅さんは7歳の時被爆し、3年を待たずに母親を亡くしている。これまで「原爆を生き延びたデザイナー」と言われたくなくて広島の質問を避けてきたという(毎日新聞)。
ちなみに竹西寛子さんは「広島が言わせた言葉の原点は原民喜の『夏の花』である」と言っている』
その日の午後、澤地久枝、佐高信共著『世代を超えて語り継ぎたい戦争文学』(岩波書店・2009年6月25日発行)が澤地さんから送られてきた。早速『原民喜の章』を開く。「夏の花」は始め『原子爆弾』の題で1947年『三田文学』で発表されようとした。占領下であったので変更されたという。この本は、いきなり原爆の場面からでなく日常描写から始まる。「私は街に出て花を買うと、妻の墓を訪れようと思った・・・」とある。自分を押さえに押さえて自分が見たものを、後に残るような、きちんとした散文で書かれる。「人類の歴史の上で初めて落とされた原爆の、その前後をこれだけきちんと描いた作品は、他にないんじゃないですか」と澤地さんは言う。
佐高さんは原民喜の詩の叙情性を指摘する。
ギラギラノ破片ヤ
灰白色ノ燃エガラガ
ヒロビロトシタ パノラマノヨウニ
アカクヤケタダレタ ニンゲンノ死体ノキミョウナリズム
スベテアッタコトカ アリエタコトナノカ
パット剥ギトッテシマッタ アトノセカイ
テンプクシタ電車ノワキノ
馬ノ胴ナンカノ フクラミカタハ
ブスブストケムル電線ノニオイ
原民喜は1951年3月13日鉄道で自死する。佐高さんは言う。『原民喜は原爆を書くために生まれてきて、なくなったようにおもえますね。おおくの作品はないけれども、原民喜というのは消えない星みたいな人ですね』。
原民喜は今なお銀河鉄道で自己完結のための旅を続けているであろうと、私は思う。
この本には五味川純平の「人間の条件』『戦争と人間』、反戦川柳詩人鶴彬の「鶴彬全集」、高杉一郎の「わたしのスターリン」「シベリアに眠る日本人」、大岡昇平の「俘虜記」「レイテ戦記」、幸田文の「父・こんなこと」、城山三郎「大義の末」その他の本が取り上げられている。私は幸田文の本は読んでいなし、これまで手にしたこともない。この本が戦争文学とは澤地は鋭い。目配りのきく人である。改めて読んでみた。なるほどと思った。城山さんと澤地さんが共に太宰治が嫌いだというのは分かるような氣がする。ともあれ、私は五味川さんの本をもう一度読んでみたいという気持ちが強くわいた。
|

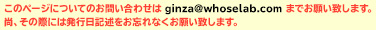
|