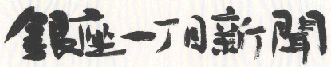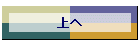
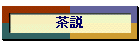
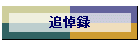
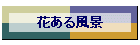
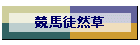
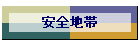
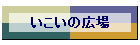
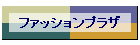
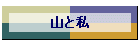
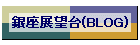
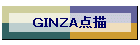
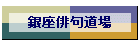
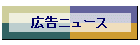
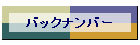
| |
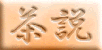
映画「ローマの教室で」に思う
 牧念人 悠々 牧念人 悠々

ジュゼッペ・ジュリアーナ監督・映画「ローマの教室で」を見る(8月23日から東京・神田神保町・岩波ホールで上映)。それぞれ個性を持った3人の校長・教師が登場する。日本の学校はどうかと考える。戦後日本の教育現場から「教師は聖職」「三尺下がって師の影を踏まず」という言葉は失われた。
映画では「教師は学校内の教育だけすればよい」という考えの女性校長も母子家庭の生徒の面倒を見る。若き国語の補助教員は「生徒にやる氣を起こさせる」とそれなりに頑張る。教育への情熱を失った老美術教師も「古典主義とロマン主義」の授業に熱を入れる。展開される映像をみながら教育となにか、と考えざるをえなかった。「人間教育」か、「学問」か、人として生きる道を教えるのが大事か、それとも勉学か。自分の学校生活を振り返ってみると、褒めてくれた先生、率先垂範の師、信頼してくれた教師などの顔が浮かんでくる。加藤周一の本によれば、府立一中時代、「生徒を独立の人格者として扱おう」とある先生が監督なしの試験を実施したことがあるという(結果は失敗に終わる)。とすれば、前者ということになる。「心を耕すことは、頭脳を耕すよりも尊い」とことわざにある。一時期「マスコミ塾」を開いたが、生徒たちに「報道の自由のために命を懸けることがある。覚悟せよ」と、第二次大戦の際のベルリン陥落の時、最後まで残り報道続けた朝日新聞記者、ベトナム戦争の際のサイゴン陥落の時、最後まで残った毎日新聞記者などを例に挙げて説明した。最近、反対の例が起きている。福島県南相馬市長桜井勝延さんが「原発事故の直後から日本のマスメディアらは現場から去っていった。戻ってきたのは6月、線量計を着けてこわごわ入ってきた」と日本記者クラブの記者会見で語っている(3月3日)。
一面、著名な作家、学者は子供頃より読書家であり、万巻の書を読破している。勉強もおろそかにできない。映画では若き国語の先生の授業で19世紀イタリアの最大の詩人であるジャコモ・レオバルディの「アジアの彷徨える羊飼いの夜の歌」が出てくる。ルーマニア人の優等生が見事暗誦する。生きる孤独を詠う長編詩だという。詩歌は現代人の嗜みである。詩歌は愛と憐みの感情を呼び起こし、他人の苦痛を察する思いやりを生む。日本の武士道も詩歌に励むのを推奨する。昭和10年代、中学校時代の担任の先生は我々に「心力歌」を教えた。「天高うして日月懸かり、地厚うして山河横はる。日月の精、山河の霊、あつまりて我が心に在り。高き天と、厚き地と、人と対して三となる。人無くしてそれ何の天ぞ。人無くしてそれ何の地ぞ。人の心の霊なるや、もって鬼神を動かすべし。人の心の妙なるや、もって天地に参ずべし・・・」中学校は千代田の城から遠くはなれたところであった。ひろきをおのれの心して務めを果たす人たらんとたゆまず励んだ。戦後、家庭を顧みずひたすら仕事に打ち込んだ。それが私の受けた教室での成果であった。「生涯ジャーナリスト」を目指す私の仕事はまだ終わっていない。
|

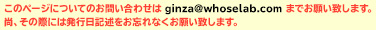
|