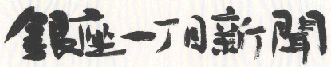|
花ある風景(526)
並木 徹
戦時中国内にあった捕虜収容所
友人安田新一君がこのほど仲間の勉強会で「大船捕虜収容所」について発表した。同期生たちは皆それぞれに目標を立て勉強しているのに励まされる。大東亜戦争中、日本国内には捕虜収容所は本所・分所・派遣所・分遣所などは約130ケ所に及ぶ。途中で閉鎖されるものもあり、終戦時には7ヶ所の本所のもとに、分所81ケ所、分遣所3ケ所があり、合計32418人の捕虜が収容されていた。終戦までに約3500人が死亡したという。
捕虜たちは日本の敗戦と同時に、アメリカ軍が日本政府に各地の捕虜収容所の屋根に「PW」と標記することを命じ、空母艦載機やB29による救援物資のパラシュート投下作戦を行った。1945年9月2日の降伏文書調印後、捕虜の集結拠点を指定し、係官を派遣して捕虜を受けとり、長崎、静岡県新居、横浜、宮城県塩竃、北海道千歳などに集め、9月中には、ほとんどの捕虜が沖縄・マニラ経由で本国へ帰還する。
安田君からいただいた資料によると、「大船捕虜収容所」の正式名称は「横須賀海軍警備隊植木分遣隊」。海軍が捕虜から情報をとるための特別の収容所で昭和17年4月に玉縄小学校の旧校舎を利用して開設された。ここに数十人から百名ぐらいを収容、尋問が終わったのがのべ408名で、そのあと各収容所に送られた。終戦時には135名が残留。ここでの死者は8名。近くの竜宝寺に埋葬され戦後、故国に帰った。現在竜宝寺には塔婆が立つ。尋問の指揮を執ったのは実松譲海軍大佐(海兵51期・昭和17年9月から軍令部五課米国班長兼海大教官)。プリンストン大学出身で、昭和15年9月から2年間駐米武官補佐官を務め、語学は堪能であった。戦後多くの著書を出す。
ここの捕虜収容所から所長の飯田角蔵少尉(絞首刑から減刑30年)ら18名が戦犯として刑を受けた。実松さんも重労働40年の刑に処せられたが昭和28年から山一証券外国部に巣鴨プリズンより通勤したという(昭和33年4月釈放)。火野葦平著「戦争犯罪人」(河出書房)には日本が独立後、管理が日本の手に移った巣鴨ブリズンでは受刑者たちの中に囚人服を背広に変えて食料品店や本屋さんに務めに出たり元軍医が病院で医者として働いたりした様子が描かれている。
捕虜の米軍兵虐待に関連して横浜軍事法廷が開かれたのは,昭和20年12月18日であった。大牟田捕虜収容所第17B分所長・由利敬陸軍中尉(絞首刑)、東京地区満島捕虜収容所第2分所・土屋辰夫衛兵(終身刑)、函館捕虜収描かれている。容所第1分所長平手嘉一陸軍中尉(絞首刑)、名古屋地方捕虜収容所、岐阜、静岡及び船津各分所長を在任した古嶋長太郎陸軍中尉(終身刑)、仙台地方捕虜収容所小名城分所長本田広治陸軍中尉の5人であった。
横浜軍事法廷は133回(昭和22年6月24日判決)開かれる。第1回の土屋辰夫の場合でもそうだがほとんど捕虜たちの誤解あるいは創作と言ってもよいもので、最初に被告にされた人たちに死刑や重罪が多い。「不幸なめぐりあわせというほかない」と岩川隆はその著『孤島の土になるとも』―BC級戦犯裁判―で言っている。
「大船捕虜収容所」について星野勇治さんが鎌倉文化研究会「鎌倉」81号に一文を寄せている。それによれば収容所の兵隊の慰問のために開かれた相撲大会には捕虜たちも見学しており、その際教えてもらった英語の単語「雲」(CLOUOD)を今でも覚えている人もいるという。また日本兵が引率して捕虜たちが防空壕堀の使役をした際、近隣の年寄りたちが交代でお茶を運んで差し入れをした。芋の粉を練って蒸した「芋団子」を「コレ ジョウトウ」と言って喜んで食べたという話もある。終戦直後の話として米軍の4発大型機からパラシュートつけたドラム缶が落とされ、農家の牛車や大八車のようなもので収容所に運んだという記述もある。
横浜軍事法廷では国内の捕虜収容所関係が圧倒的多数を占める。件数222件、被告数475人、有罪453人(うち死刑29人)、無罪19名、起訴取り下げ3名となっている。絞首刑を宣告され断頭台の露と消えた平手嘉一大尉は(昭和21年8月23日執行)「ますらをの道にしあればひたすらに務はたして今日ぞ散りゆく」という辞世の歌を残す。由利敬中尉(昭和21年4月26日死刑執行)もまた「死するに非ず。大生命の本源に帰するものなり。ただ物質なる肉体のみやむなくポツダム宣言の露と消えん」との遺書を書いて死んでいった(前掲岩川隆著書より)。大和男子の死に際はみな潔かった。
|