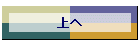
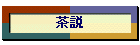
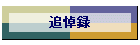


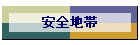
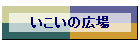
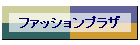
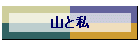
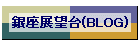

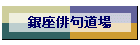
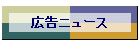
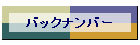
| |

「一字の師」が欲しい
 牧念人 悠々 牧念人 悠々

文章を書く上で一番悩むのは書き出しである。「書き出し」がうまくいけばあとはさらさらとうまくいく。ブラジル移民を描いた小説『蒼氓』で第一回芥川賞(昭和10年)を受賞した石川達三は小説の「題名」が思い浮かべればあとはスムーズに書き上げたといわれる。
文章には書く人の人柄があらわれる。その人ならでの工夫も施されているし、文体もあり、生き方も表明されている。文章の訂正は細心の注意がいる。当然筆者の了解もいる。それが常識と言うものである。
晩唐の時代、僧斉己が「早梅詩」を詠んだ。
「前村、深雪の裏
昨夜、数枝開く」
これを見た詩人、鄭谷が「数」を「一」に直した。「早咲きであるから数枝より一枝のほうが確かにしまった感じがする」それゆえに鄭谷を『一字の師』と言われた(陳舜臣著『弥縫録』・中公文庫)。
私は雑誌『偕行』6月の「花だより」の59期生の欄に担当者の梶川和男君に頼まれて、亡くなった奈良泰夫君の葬儀の際に読んだ弔辞を掲載した。原文には「俺もあと34年後にそちらに行く。もうしばらく待ってくれ。合掌」とあった。最終校正で梶川君もそれを確認した。ところが雑誌が出てみると、『34年』が『3、4年後』に直されている。梶川君が調べたところ 編集委員長が担当者にも筆者にも断らず勝手に訂正したという。このようなことは雑誌編集上許されることではない。私は平成21年1月の『偕行』で歳男の「年頭所感」を述べた。その中で『一応120歳まで生きることを目標としており、天寿を全うしたい』と書いている。この時の編集委員長は現在も同じ人である。3年も前のこととはいえ、その時も私の文章を読んでいる。執筆者の人柄がわからなければおかしい。あと34年と言うことは120歳まで生きるということかと理解できたはずである。
雑誌『偕行』に「一字の師」を求めるのは無理な話であろう。むしろ『3、4年の愚』に甘んじるべきなのかもしれない。「生涯ジャーナリスト」を目指す私には『一字の師』が欲しい。
|

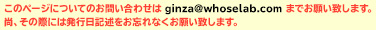
|
