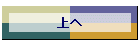
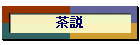
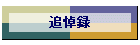


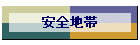

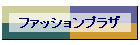
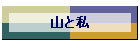
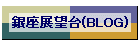

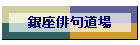
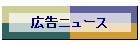
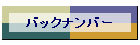
| |

イラクの米軍
「爆弾処理班」の死と生
 牧念人 悠々
牧念人 悠々

イラク開戦以来、米軍の戦死者は4千人を超える。半分近くは即席爆弾によるものといわれる。バクダットはじめ各地での「自爆テロ」も後を絶たない。2001年9・11事件から「テロとの戦い」はいまなお続いている。戦争のすさまじい死の恐怖の現実をまざまざと見せたのが米軍の「爆弾物処理班」の活躍を描いた映画「ハート・ロッカー」(キャスリン・ビグロー監督・3月6日から全国公開)である。
時は2004年夏、場所はイラク・バクダット郊外。主人公は爆発物処理班・ブラボー中隊のジェームス・二等軍曹である。爆発処理中、戦死した(映画のカタログでは「急死」とおかしい表現をされている。)班長トムソン軍曹の後任として赴任してきた。ともかく変わった男である。爆弾処理するにはルールやチームワークが必要なのだが、ジェームスはことごとく無視する。部下のサンボーン軍曹とエルドリッジ技術兵を恐怖と不安に陥れる。住宅街のモスク近くで発見された爆弾処理には確認のための遠隔ロボットも使わず、煙幕弾で目くらまして近づき、現場に突進してきたタクシーに拳銃を突きつけて追い返す。地中に埋まった6つの爆弾を処理する。あるときは、怪しげな荷物を積んだ無断駐車の車を調べようとすると、テロリストが発砲、車が炎上する。現場が騒然とする中、ジェームズは消火器を使って火を消しとめ、後部とランクに積まれた爆弾を発見、作業するのに面倒とばかりに防護服を脱ぎ捨て、車内に隠された起爆装置を解除する。豪胆といえば豪胆、無鉄砲といえば無鉄砲な振る舞いである。これまで処理した爆弾は873個にのぼる。勇気をたたえる上官から「爆弾を処理するのに一番大切なことは何か」と問われて「死なないことです」と答える。死を超越してはじめてよい仕事が出来るということか。死を恐れていては仕事にならないということか。
ここで思い出した。サリン事件の際、地下鉄のサリン駆除に陸上自衛隊の科学学校の防疫班が出動、地下鉄の車内を消毒した。完全に消毒したかどうかは人間の手で確認するほかない。班長が敢然として手袋を脱いで確認した。このようなことを一般紙は全く報道しなかった。ニュースにならないということか。日本でも取り上げれば映画にはなる。
砂漠地帯でテロリストに襲われ無事窮地を脱して基地に帰還したブラボー中隊の3人は酒を飲みまくる。地獄の瀬戸際まで追い詰められた恐怖、生への執着、戦争への疑問などが彼らを酒に追いやったのであろう。それしか戦場では特効薬がない。
不発弾回収作業中にビルの一室で”人間爆弾”になり損ねた少年の死体を発見する。ジェームスは腹部に収められた爆弾を取り出し死体を白布で包んでやる。この作業についてきた軍医が住民に紛れ込んでいたテロリストの爆弾で戦死する(映画のカタログでは「殉死」と説明されている。おかしい表現である)。軍医の体は一瞬にして消滅する。退屈しのぎでついてきた軍医が戦死する戦場の不条理を示す。その夜、米軍の緩衝地帯で起きた大規模な爆発事件でジェームスは、テロリストへの怒りを爆発させて、任務外の犯人追跡作戦をする。成果は犯人を取り逃がし、エルドリッジが足に重傷を負っただけであった。最後のシーンに登場するのはシャツの下に大量の爆弾を仕掛けられた男の救出劇である。男は「死にたくない。家族がいる。見捨てないでくれ」と叫ぶ。爆弾は厳重にロックされ簡単に切断できない。時限装置のタイマーはあと2分。ジェームスは最後まで解除に努力するがあと数秒であきらめて退避して助かる。映画は迫力あるシーンが次から次に展開される。3人の兵士の戦場の苦悩、心の葛藤をさまざまな形で表現する。ともかく戦場の恐るべき実態が明らかにされている。「イラクに来たってことは、死ぬことだ」という言葉は胸を打つ。戦後65年一人の戦死者も出さず、平和に酔いしれている日本は今なお続く自由諸国対テログループの戦いを忘れてはなるまい。
|

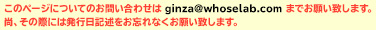
|
