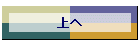
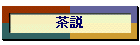



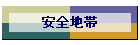
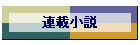

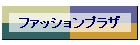
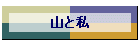


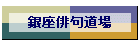
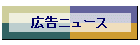
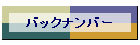
| |

記者達よ ハンターになれ!
 牧念人 悠々
牧念人 悠々

新聞記者ものや戦記物を読むと何故か、心が躍る。元・毎日新聞主筆木戸湊さんの回想録「記者たちよ ハンターになれ!」(新風書房刊平成21年5月10日刊)は「懦夫を立たしむるもの」がある。表紙の扉に曰く。「相次ぐ虚偽証言に揺らぐテレビ界、朝日新聞襲撃事件の偽犯人にコロリとだまされる週刊誌・・・ジャーナリズム崩壊の声が日増しに高まっている。崩壊防止策は記者クラブやインターネット依存から脱却して人間(ジンカン)というジャングルに飛び込み己の足と才覚で”真実のニュース”という獲物をキャッチすることだろう。今日ほどジャーナリストに果敢なハンティング精神が要求されている時はないのだ」。この本こそ「己の足と才覚で掴んだ」真実のニュース取材物語である。若い記者達は共感した所に赤線を引き拳々服膺したらよい。伸びる記者とそうでない記者の相違はここにある。様々な貴重な取材方法と問題解決の対応、処理方法が書いてある。
記者・部長・局長・社長時代、幾度となく名誉毀損、記事訂正などで当事者と交渉した私は「記事が真実であると信ずる限り」妥協しなかった。もちろん少ないが訂正記事も書いた。木戸さんの場合、地検に呼び出されて名誉毀損容疑で取り調べを受けたと言うから問題は深刻だ。問題の記事は和歌山市のある地区で前科3犯の暴力団員が自治会長に選ばれ、自動的に防犯委員になるので警察が苦慮していると言うものであった。もちろん「暴力団リスト」を見せて貰って確認した上、記事にしたものであった。ところがその暴力団員から名誉毀損の告訴状が出ると、県警本部長は暴力団員と親交のある有力議員の質問に「暴力団のリストはあるともないともいえない。あったとしても外部に見せるべきものではない」と答えた。このため地元署も後難を恐れて沈黙。挙げ句の果てに暴力団員に署長が「あなたは現在暴力団員ではありません」という一筆まで書く始末であった。木戸さんを救ったのは地検の次席検事の「暴力団員と信ずるに至った”証拠“がほしいね」という言葉と木戸記者が粘った末「暴力団のリスト」を見せてくれた所轄署の初老の刑事の情けある処置であった。その刑事が「宿直の日に来いよ」というので行くと「署の風呂に入ってくる。電話と書類の番をしといてくれよ」とその刑事は出て行った。そこに暴力団のリストがあった。早速それをカメラに納めた。この写真を地検に提出して不起訴処分となった。刑事は何故、木戸記者に情けをかけたのか、「あなたの年が亡くした子と同年と知って『もし息子も生きていたらあんな青年になっていたんやな・・・』があの人の口ぐせだったのよ」と言う刑事の奥さんの言葉が泣かせる。これはまさに一編のドラマである。
木戸記者はかなり強引で機転の利く記者のようである。よく言えば『豪腕』である。1977年7月起きたパキスタンのクーデター取材にその思いを強くする。ジャカルタ支局長時代の話だが初めての異国の土地で知己も取材源もない木戸記者が飛び込んだ先が「パキスタン・プレス・インターナショナル」だ。そこでロンドン大学に6年留学していた政治部デスクをスコッチでホテルに誘い込む。この国は禁酒国である。効果抜群。最新のクーデター情報や政権の経済政策の失敗などのバックグラウンドまで取材する。それだけではない。失脚したブット首相の行き先まで突き止め現場まで出かけ「ブットなお生存」の特ダネまでものにするのだから見事というほかない。木戸記者の徹底した現場主義には脱帽である。
大阪社会部でも数々の特ダネを連発する。大阪編集局長時代に阪神大地震が起きたとき『希望新聞』を設けたのは面白い。社会部長、特別報道部長、学芸部長の発案と言うが、ある大学の教授が『新聞の”原点”を見た思いがする』と言ったように現在の新聞は市民や庶民と密着した生活問題と取り組む、この原点に戻るべきだという気がしてならない。ジャーナリズム崩壊を防ぐ一手は『現場主義』しかない。久しぶりに血が騒ぐのを覚えた。
|

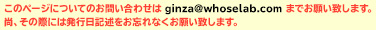
|
