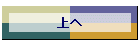
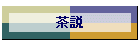
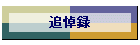


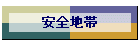
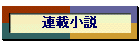

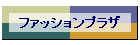
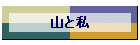
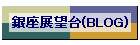

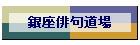
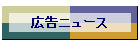
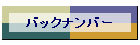
| |
|
〔連載小説〕
VIVA 70歳!
さいとう
きたみ著
第二章 (つづき)
春介:その2
春介には社会人になった息子が二人いる。長男は何年かかかったが念願の司法試験を通り、東京の弁護士事務所でいわゆるイソ弁をしている。弟は商社勤めで今はイランで難しい業務についている。一回り年上の妻、桜子は東京のアパートで独り暮らし、どうにか元気に市民文化活動などをしている。春介が桜子と結婚したのは大学生の時であった。春介がアメリカに初めてわたったのは小学校四年生の時であった。いわゆる帰国子女の第一号であったと思う。小学校を終えてから日本の中学へ入っての英語の授業にはほとほとまいった。
当時の英語の先生方は喋れないのはもとより、学力そのものもかなり程度が低かった。水曜日をスペルどおりにウエズネスデイと発音を強いられた時には完全に打ちのめされた。教師の方もアメリカ帰りの春介を意識するあまり妙に卑屈になったり突然居丈高になったり難しい存在であった。英語が喋れない風を装うのも容易とは言えない演技ではあった。その延長は高等学校でも続いた。今度はそこそこ自分の英語力に自信を持っている先生方との対応であって、これにも工夫を要した。“If
I were a bird, I could fly to you”
などという仮定形の文章などは小学校レベルの英語力ではいわば文語に近く春介の理解を超えた。文法が苦手と知った教師たちはことさら難しい設問を春介に集中するようになったし、当時まだ米語より英語が主流にあった教育方針もありアメリカ語を話す春介はことごとく厭味を聞かされるのであった。受験校であることを天下に公言しているこの高校への入学は春介にとって間違った選択であったのかもしれない。一学年男子300人、女子100人の編成で、本人が強くアッピールしない限り全員東大への願書が提出される慣わしであった。
通学する救いは冬彦、夏雄という親友に出会えてことにあったが、全体としては決してバラ色とは言えない高校生生活であった。兎に角、東大に入ることが主目的であるから、他のことごとは全てその大目的のために無価値なものとされ、受験勉強以外のことに関心を持つ者は変人扱いされるか異端者のように見られる。早々に春介はアメリカ留学を目標に定めた。結果的に冬彦は東大に行くが夏男は慶応に行った。しかし読書家である冬彦や多趣味の夏男とは受験勉強以外の様ざまなテーマを話し合うことができてその点は幸せだったと言える。演劇部のために夏男が長い芝居を書き、春介が演出し、冬彦が装置を受け持つという楽しい体験もあった。
アメリカ留学後の最初の夏休み、春介は一年半ぶりに日本に帰って来た。アメリカのキャンパスで知り合ったかなり年上の日本人の先輩に連れられ新宿のバーに行き、そこで妻となる名物ママの桜子に会い電撃的とも言える恋に落ちた。桜子は春介よりも一回り12才年上であった。若い頃、宝塚の男役スターであって、退団後、映画や舞台の女優となり高名な中年の演出家と結婚をし、何があったのかすぐに離婚をしてこのバーを開店した。客には演劇関係者も多く、当時、大いに流行っていたバーであった。宝塚時代を彷彿とさせる男仕立てのスーツなどで小気味よく客をさばくその言動は春介にはひどく魅力的に映った。
たまたま日本人の仲間と来ていたアメリカ人の客と対等に会話する春介を桜子も関心を持って観察していた。夏も終りとなりアメリカに戻るまでわずかの日数になった。それまで連日のように通っていた春介だが二人にとって運命的な日は荒れ模様の天候であった。台風だったのだと思う。どしゃぶりの雨にもなり、さすがに客足は少なかった。早仕舞いのため春介も手伝って戸締りをはじめた時には従業員たちも早く帰り桜子と二人だけになった。
「ゆっくり飲もうか」
と言う桜子の誘いに春介は異存のあるはずもなかった。その夜はいつもの男っぽいスタイルではなく黒いレースのワンピースに金色のハイヒール姿がなまめかしかった。やがて酔った二人は唇を寄せ合い熱く抱き合うこととなった。今でもその時の彼女を想うと興奮が蘇える。スカートをたくし上げ、狭いカウンターの上に膝を大きく開いて仰向けに横たわり、春介を見つめた。カウンターの上の不自由な姿勢のまま、春介は激しくママを抱き、荒々しく動いた。彼女も何度も何度も嗚咽をもらす。こうして桜子と春介のやや不思議な結婚生活がはじまったのだった。何故、初めての情事に求婚などしたのか、今も判然としないが、兎に角彼女だけでなく、彼女の居る世界そのものが全部欲しかったのだと思う。
桜子と春介の結婚は周辺に多少の衝撃を与えたが、春介がアメリカの学生生活に戻り、帰国しても店には原則として顔を出さなかったので、従前のように客足は戻った。二人の息子にも恵まれ夫婦関係はしごく順調に思われていたが、二人には二人だけの口には出さない決まりごとがあった。二人の異性関係は二人の自由であるということだ。若い春介が異国に於いて多少の異性関係があるのはある意味で自然のことだと桜子は考えたし、桜子も水商売をしている以上絶えず酔った男たちと接するわけだから何か生じうる環境にある。
わけても桜子の店の客の多くは桜子を目当てにやって来るのだから彼女もそれを十分承知で、それぞれの客に喜ばれる態度をきめ細かくとっている。客との間に何かが生じても、これまた、さして不自然なことではないということが春介にも理解できた。桜子82才、春介70才の今日まで離婚することもなく離婚話さえもなく続いてきている。その間、それぞれの情事がそれぞれの相手の知るところとなったこともあったが、お互いにそれについて言及することはなかった。他人ごとに口を出したがるお節介も多く、いろいろと噂話を告げ口に来る連中も居たが、二人は二人の秘め事として干渉しないのだった。春介が日本に居る時でも桜子が自宅に戻るのは夜が明ける時刻でもあり、店を休む土・日にはおおむね春介の仕事が入る。毎晩毎晩愛し合おうね、などと約束した新婚の頃のことを思い出し、二人で苦笑しあったりもする結婚生活だった。桜子の異性関係についてはもう一つ許せる、いや許さざるを得ない体験を春介は数多く持っていた。春介にとって最も容易に口説ける異性が実はバーのママたちだったのだ。どんな小さな店であれママとなればそれが自前のものである以上、一国一城の主だった。スタートに於いて決して少額とはいえない費用も要したことであろうし、水商売を主業とすることにそれぞれ長い熟慮やためらいもあったことだろう。おおむね自分より若い娘たちを使わざるを得ず、当然客たちにもてるその若い子たちにママとして張り合って行かねばならない。ツケをためる客もいる。悪酔いしてトラブルを起こす客もいる。いずれにせよ酒場に来る客たちは何らかの彼ら自身のストレスの解消が目的であるのだから甘えん坊だったり愚痴っぽかったり手前勝手だったりする。毎晩毎晩そういう客たちの相手をしているうちに自分自身が一番可哀相に思えてくる。そんな時、好感のもてる客から親切にされるとぐっと来るものがある。しかし水商売にとって異性とのスキャンダルはタブーだ。一人の客と出来てしまったため全ての常連客たちに逃げられた例をいくつも見てきている。支払いもきれいで、好ましい客の中でも、仮に彼と情事を持っても絶対に秘密を守ってくれる客でなければならない。春介はまさにそういう条件にぴったりなのだ。彼は決して自分の情事を口外しない。時折、女性と同伴で店に現れてもその女性と何かがある風情はかけらほども見せようとしない。例えその同伴女性が二人の関係を見せびらかすように春介に媚態を見せても実にスマートにそれを回避する。そうしてママは自らの意思で春介に抱かれることになる。春介が相手になったママたちもそれぞれ魅力的な女性だったが、客観的に言って桜子の美貌は群を抜いていて、男っぽい気風のよさも見事である。通常の男ならば口説いてみたくなるのは当然である。肝心の亭主である春介が不在がちなのであるから、桜子がつい上客の中の誰かに心も体も許すことはむしろ自然なことなのかもしれない。自らの体験を通してそう思う春介だった。それに春介は自分でもいつも思うのだが嫉妬心というものに欠落している。同性、異性を問わず嫉妬という感情を抱いたことがほとんどない。
春介の恋の相手は依然バーのママが主流であったが、国際線のスチュワーデスとも随分付き合ったものだ。但し、彼女たちを口説くには一つのコツがある。まずフランスへ行く時はエア・フランス、イタリアに行く時はアリタリアというようにその国のエアラインを選ぶ。長時間の海外勤務が終り、母国へ帰れる安堵感が彼女たちをやや幸せにしている。一般サラリーマンの金曜日の午後にあたるのかもしれない。ねらいの女性と話せる機会が来た時、実は君の国に行くのは初めてなのだ、と切り出す。まだホテルも予約していないし空港に着いたらレンターカーを借りなければならない、などと多少不安げに伝える。早朝や深夜の離着陸もあるからだろうが、彼女たちの多くは自宅とは別に空港の近所に小さなアパートを借りている例が多い。何だか国際規約のようなものがあるらしく、海外勤務を終えるとクルーたちは最低48時間以上の休暇をとらねばならないらしい。まさに金曜日の午後なのだ。私、車を空港に持って来ているし、狭いところだけど私のアパートで良ければ何も高いホテル代を払うこともないんじゃない、美味しいレストランも紹介してあげる、という段取りになる。ファーストクラスのスチュワーデスは一般に若い子よりも、ややベテランが多い。長くこの仕事を続けているということは独身か、人妻であっても亭主との別居に慣れている。かくして、ホテル、ガイド、ドライバー、通訳、そして愛人のすべてを手にいれることになる。勿論、ファーストクラスに乗る日本人は、そこそこリッチでとんでもない人物ではなかろうという彼女たちなりの計算もあることだろう。旅が多いアメリカ人の友達も全く同じようにしていると聞き、二人で過去の思い出話が大いに盛り上がったものだ。スチュワーデスという仕事が日本と比べて、必ずしも高く評価されていないし、収入も決して多くはない。悪い表現をすれば乗客をカモにしようという魂胆も彼女たちにはあるだろう。身分が知れている以上、そう出鱈目はできない。後に会社に訴えられたりしたら大事だ。せいぜい高級レストランでの会食をねだられるぐらいがオチだ。ただ気をつけなければならないのはインドだったかアフリカだったか実家に連れて行かれ、大家族みんなに紹介され彼ら全員を日本食レストランに招待せざるをえないハメになったことがある。
旅ではいろいろの人たちと出会う。春介の体験では、いわゆる知的な仕事についている女性たち、大学教授や弁護士などが、比較的容易にベッドを共にしてくれる。欧米では男女平等が随分進んでは来ているが女性が一人でレストランやバーに出入りすることは何となく一般的ではない。単に好色であるというのではなく旅先で男のパートナーを得るというのは、一つの生活の知恵なのかもしれない。
何故、情事を重ねるのか、春介にとってそれは何故、酒を飲むのかと問われることと似ている。酒の酔いには情事の酔いに近いものがある。一言でいえば論理から抜け出る曖昧さである。人生の中で曖昧さというものに絶えず遭遇し思い悩むことがあるが、酒と情事は初めからその曖昧さを求めている。人生が一つのドラマでしか無いとするならば、情事はドラマの中のドラマ、劇中劇のようなものなのかもしれない。
桜子が75才まで続けていた店をやっと引退し後輩に店を託した頃、春介は久々に自宅に帰った。夜も遅く桜子はあたかも長年の睡眠不足を取り戻すかのように早くもベッドの中だった。寝る前に読書でもしたのか枕もとのスタンドの光は彼女の寝顔を照らしだしていた。
そっと隣に横になり、その寝顔を見つめた。美しい桜子も化粧を落としたその寝顔は正直に年齢を表している。何か夢を見ているのか少し表情を変え、春介の方に寝返りを打った。
春介は彼女の寝顔から目が離せなくなった。深い皴が黒い線となって縦横に走っている。入れ歯をはずした口もとは落ち窪んでいる。細い首筋が呼吸とともにひきつれている。時間にしたら30分ほどでしかなかったのかもしれないが、春介はこの女性との出会いから現在までの50年にわたる歴史を全て反芻しつつ長い間彼女の寝顔を見つめるのだった。母親に対していた時にも似てしみじみ自分の身内、それももっとも長く親しい相手として、ああ、これが俺の女房なのだという感謝や謝罪などが入り混じった決して軽々しくない深い愛情とともに見つめ続けるのだった。いつも漠然たる孤独感は彼の人生を占めているがこの時ばかりはこの人と共に歩いて来た人生であったと強く思うのだった。春介はわずかではあるが目尻に流れ出てきた涙を指ですくうとそっと桜子の額にそれをなでつけるのだった。
(つづく)
|

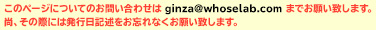
|
