緯度では亜熱帯でも、さすがに冬至近くともなると日の傾くのが早い。つい先程までポロシャツ一枚でも汗をかくほどだったのが、それまでの日差しが山に遮られると、冷気がどこからともなく襲ってきた。慶太は腰に巻いていたセーターを頭からかぶった。
トリジャの家では、慶太を待っていた父がどうぞ、どうぞという手招きで、部屋の中へ招き入れた。八畳程の土間になった部屋の中央にいろりが掘ってある。母が器用な手付きで、そばに積み上げた柴を折ってはいろりにくべた。オレンジ色の炎が上り、五徳の上の水を入れた鍋を包む。母は客人にお茶を振る舞うべく、湯をわかし始めたのである。十分な火が出来たことを確認した母は、傍らの缶の中からドーナツ状になった揚げ菓子を取り出して、ステンレスの皿に載せて慶太の前に差し出した。シェルと呼ばれ、朝食と夕食の間が長いネパールでは、午後水牛のミルクを入れた紅茶のチャーと共にこれを食べて、夕食までの時間をつなぐ。それを一つ手にとって、ちぎりながら食べ始めると、母が豊かな香りをたてる鍋の紅茶をステンレスのカップに注いだ。
「これをいただいたらすぐ失礼します。ゴルカまで戻らなければならないので」
慶太が父に告げた。父はにこにこしながら、
「ゴルカに戻ることはない。今日は遅い。あなたの寝る部屋はあるから、泊まっていって下さい」
と言った。その口調には、選択はそれ以外にはないと申し渡すような感じがあった。父も母も彫りの深い整った顔をしている。トリジャの大きな目は母に似ていた。しっかりとした眉と鋭角的な細く高い鼻、それに長身なのは父親譲りのようであった。
慶太は出発すべく、立ち上がった。土間から軒下に出ると、一緒に出てきた元グルカ兵の父は山影の伸びる谷間を見やりながら、
「今日はもう遅い。ぜひ泊まっていって下さい」
と再度言った。その時隣の部屋から、トリジャが出てきた。トリジャは大きな黒い瞳で慶太をじっと見た。その目はまだ話していないことがあると暗示しているように感じられた。咄嗟に慶太は予定の変更を決断した。客人となることを父に告げると、父は褐色の端正な顔をほころばせた。久しぶりに遠来の客を迎える喜びと興奮を味わっているような笑顔だった。トリジャもどことなく安心したような柔らかい表情になった。
その晩慶太はいろりを囲んでロキシーとダールバートをごちそうになりながら、退役までインドのグルカ部隊にいた父の話しを聞いた。退役後は年金とわずかな農業で慎ましく生活をしているが、マヘシュやトリジャのような子を持つ元グルカ兵は大いに恵まれている方だった。父はいつまでも昔話を続けたがったが、それに付き合うと、母やトリジャの食事の時間がなくなる。慶太はロキシーのグラスを持って外に出て、庭の床几に座った。セーターの上に防寒用のジャケットを着ると、寒さは問題なかった。ロキシーが体を中から温めてくれたせいもある。
ロキシーのお代わりを持ってきたトリジャに、食事の後片付けが終われば少し話しをしたいと言った。その時は恥ずかしそうに笑っただけだったトリジャが、慶太がぼんやりと座っていると、頭からスカーフを巻き、ヤクの太い毛糸のセーターを着て出て来て、慶太の横に座った。
「トリジャは英語がとっても上手だけど、どこで勉強したの?」
トリジャは十六歳でゴルカの高校を出た。兄の紹介でネパール赤十字の家族計画指導補助員の訓練をカトマンズで受けることになった。その時英語学校に通った。その後ゴルカを基地に、外国から来る家族計画や医療の多くの専門家に付き添って、マナスル、ヒマルチュリ山麓の村を回った。この時耳から実用的な英語を学んだ。三年たって、今度は飲料水衛生計画がカナダの協力によりポカラ周辺で始まって、トリジャはタナフン郡担当としてドルフェルディ村を基地に活動した。しかし父が決めた結婚のためにゴルカに戻る。高校の先生だった夫は、一年後カトマンズの学校に転勤した。既に小学校の先生になっていたトリジャはそのままゴルカに残る。ネパールでは初等教育の教師は必ずしも教師としての専門的訓練を受けていない。代用教員は全国で全教師の半数近くにもなる。
昼間よりも気軽に自分を語ったトリジャが、
「リリジャと私とは、一つ共通点があるの」
と言った。
「リリジャと共通点?」
「そう、同じなの」
「例えば二人とも美しくて、頭がよくて・・・」
慶太はトリジャの気持ちを和らげるようにこう言うと、トリジャは嬉しそうな笑みを浮かべながら、否定した。
「それでは何?その二人の共通点って?」
一呼吸間を置いて、トリジャが言った。
「二人とも離婚したの。ディボース。二人とも離婚経験者なの」
トリジャはゆっくりと言って、黒い目を慶太に向けた。慶太がどんな反応をするかを楽しみにするような目だった。
「そう、二人とも。トリジャのことはマヘシュから聞いたけど・・・」
「結婚はよくない。幸せになるよりも不幸になる」
トリジャがしんみりと言った。トリジャのように、子供が出来ないからと突然離縁を言い渡されるような社会では特にそうだろう。慶太にはトリジャの言葉が心にしみた。
「リリジャという人も離婚したの・・・。そうだったの・・・、リリジャ・・・」
慶太はゆっくりと何気なく口にして、はっと息をのんだ。何か気になっていたが、リリジャと自分で発音しているうちに、このネパール語のような名前が突然因数分解されてきたのである。リリジャ。リリジャとは、リリ・ジャ、リリー・ジャ・・・。リリーとはユリの花のことではないのか。慶太はびっくりした。ドクター・ヤマムラとトリジャが言うので、すっかり人違いを納得していた。リリジャなどと言う日本人の名前などもちろんない。それはネパール人にも親しみやすいようにつけた愛称であることは明らかだ。とすれば、百合の英語のリリーにネパール流の語尾のジャを愛称としてつけたと考えることは大いに可能だ。
しかしもしそうだとしたら百合がなぜドクター・ヤマムラ?リリジャが百合なら、なぜオオヤマでないのか。なぜドクターなのか。慶太が頭の中であれこれ思いを巡らせていると、トリジャが、
「私が別れたのは去年。リリジャは今年。リリジャもかわいそうな人。時々とっても寂しそうな顔をする」
と言った。
「トリジャ、その人、リリジャ。リリジャが離婚したのは今年って言った?」
「そう、今年の春なんだって。五月から私と一緒に調査を始めた。それで四月に一度準備のためにネパールに来たの。離婚したのはその前だって」
四月の前、ということは三月かそれとも二月か。いやそれより四月に一度準備でネパールに来たって?そして五月から調査?突然慶太の体の中を高ボルトの戦慄が突き抜けた。
離婚、四月、五月・・・。
ドクター・ヤマムラ、ユリ・ヤマムラ・・・。それは離婚後の名前ではないのか。いや結婚前の名前ではないのか。ヤマムラ・ユリ、オオヤマ・ユリ、山村百合、大山百合。トリジャの話しから山村百合を大山百合に置き換えればすべてが符号する。二つの名前が同じ人でなければ、こういう符号はあり得ないではないか。慶太は興奮で震えた。体が引き攣ってくるのが分かる。手も、足も、口も自由がきかない。大山百合、いや山村百合、その百合を知っている可愛いネパールの娘が今目の前にいる。
『トリジャ、百合は今どこにいる?』
慶太は叫んだ。もちろんそれは声にはならなかった。
慶太の様子が一変したのはトリジャにも分かった。慶太に何が起きたかも分からず、トリジャは不安な面持ちでただじっと慶太を見詰めるだけだった。
「トリジャ」
慶太は激してくる感情を懸命に抑えて、話し出した。
「トリジャ、トリジャはね、今とっても重大なことを話してくれた。リリジャは四月ネパールに来る前に離婚したと言ったんだよね」
トリジャの顔を見ながら、慶太は自分が聞いたことを確認するようにゆっくりと話した。
「トリジャ、そのリリジャはね、やっぱり私の探している人だ」
慶太の言葉に、トリジャはハッと驚いたように、スカーフを口にあてた。
「ドクター・ヤマムラというのはね、離婚してそういう名前になったんだ。いや、これは正確な言い方ではない。その人の元の名前はね、ユリ・ヤマムラって言うんだ。結婚してユリ・オオヤマという名前になった。でも離婚したのでまた元のユリ・ヤマムラに戻った。トリジャの知っている人と、私の知っている人とは別人のようにみえたけど、そうじゃないんだ」
慶太は大きな深呼吸をした。
「ユリというのね、英語で言うとリリー、トリジャも知っている大きくきれいな白やピンクの花びらを持つ花。それをトリジャのようにネパール式に呼ぶとリリージャになる」
トリジャは不思議そうに、ユリ、リリー、リリージャと復唱した。
「そうそう。その人は今ネパールにいることを人に知られたくないから、わざと日本人のようには聞こえない、いや日本人と分かってもユリという人とはわからないように、リリーという英語にして、トリジャたちにも親しまれるようにネパール式にしていたんだ、きっと。それでリリジャは今どこにいるの?」
「・・・」
「トリジャ、ようく聞いて欲しい。わたしはとても大事なことでその人に会いに来たんだ。わたしはもうあまり長くネパールにいられない。だから一日も早くリリジャに会わないと、時間がなくなってしまう。もし会えなかったら、今度いつどこで会えるか想像も出来ない。その人はどこにいるかしら?」
「・・・」
「トリジャ、リリジャはね、わたしに一度手紙をくれた。それはボンベイからだった。トリジャに話したように、離婚したこととか、しばらく日本を離れてこれからどう生きるかなどを考えたいと、書いてあった」
「ボンベイ?」
「そう、ボンベイから。六月の末に出した手紙だった」
「リリジャと私は一週間デリーとボンベイに行ったの。本格的なモンスーンの雨になった時、六月末」
「そう、それでリリジャとわたしの探している人とがまったく同じ人だというのが確実になった。トリジャはさっき、リリジャもとっても寂しそうにするって言ったよね。そう、リリジャも離婚したこと、前の仕事を止めたこと、一人でネパールにいることなどを考えて、寂しくなるんだ。そして誰かに聞いてもらいたいはずなんだ。トリジャだって、そんな時誰か本当に親しい友達が欲しいと思うだろう?」
「・・・」
「わたしのことをリリジャが今どう思っているかはよく分からない。でもわたしはリリジャと四月にアンナプルナのトレッキングを一緒にして、いろんなことを話し合った。手紙でもリリジャは悲しいことも正直にわたしに書いてくれた。だからわたしがリリジャに会いに来たことが分かると、リリジャはきっと喜んでくれると思う」
「リリジャは時々トレッキングの話しをした。国連の人と一緒に行って、いろんな話しをしたんだって。ネパールで仕事をしようと思ったのも、その国連の人と話し合ったためだって」
「そう、その国連の人というのはわたしなんだ」
「・・・」
「だからトリジャ、わたしにその人がどこにいるか教えてくれない?」
「・・・」
「トリジャは、わたしを見てリリジャが悲しむと思う?」
「・・・」
「もしトリジャがリリジャだとしたら、ニューヨークからわたしが会いに来たら、帰れって言う?」
トリジャは染色の粗い太い毛糸のセーターの袖口を折り返したり、伸ばしたりを繰り返しながら、慶太の問いかけを聞いていた。時々何か言おうとして、慶太の顔を見上げることがあるものの、すぐ目を落とした。
山の陰に小さな月があるのか、トリジャを探しに行った南の斜面やその下の谷が、ベージュの薄いベールをかぶせたように淡く光っている。しじまを抜けてくる谷川の音だけが冷気を揺らす。慶太が沈黙すると、トリジャの息が聞こえた。
「リリジャが・・・」
トリジャはその静けさの中でもほとんど聞き取れないような小さな声で話し出した。
「リリジャは一人日本人の友達を持っている。女の人。日本の国際開発庁のボランティアの人。ポカラの北のカスキ郡の村に住んでいる。仕事で村を回らない時は、その人の家に行くの。ポカラは日本から来る人も多いから、よくないんだって」
「そう、それで、トリジャはそのカスキ郡の村って知ってるの?」
「カスキ郡モージャ村。冬はビジャヤプル・コーラの流れが小さいので、河原を車で行く。それから山を登る。二時間半歩けば行ける」
「それでその国際開発庁のボランティアの人の名前は何ていうの?国際開発庁は普通ジャイカって言ってる組織のことだと思うけど」
「そう、ジャイカ」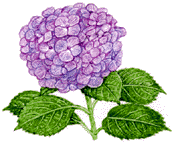
「で、その人の名前は?」
「チェリー」
「チェリー?」
「そう」
「トリジャ、ありがとう。トリジャに会えて本当によかった」
