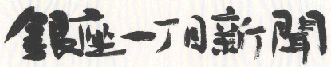13年の1月20日号から「お耳を拝借」の連載を始めてちょうど1年になります。良く続いたものだと自分でも感心していますが、その代り困った時の何とやらで勝手に周囲を巻き込むので、断りもなく材料にされる側はいい迷惑のようです。特に何回も俎上に上がった娘など、原稿料を半分よこせなどと言っています。いつもいつもネタを探し回っているわけではないのですが、電車の中でふと目にした事や、誰かのちょっとした言葉がヒントになることが往々にしてあります。
スポーツニッポン新聞と協力して開校している「スポニチ・マスコミ塾」は、ジャーナリストの養成を目指していますが、その目玉になっているスポニチ編集委員の実践的文章講座は受講生に大変喜ばれているものです。
その教材の中に<名文を書こうとせずに、悪文を書かないように>というのがあり、悪文を回避する方法として、
読み手を意識する。読み手に分かりやすく、要点を明確に。
書き出しの3行が勝負。
持って回った表現やひとりよがりの言葉や表現を避ける。
同じ言葉・表現を繰り返さない。
長い文章(800字以上)では、結論を先に言う。
などがあります。
これは容易いようで難しく、同じく我が社で開講しているEメールによる「作文添削教室」でも、400字の短い文章の中に同じ言葉が何回か繰り返されていることを注意されているのなどをよく見かけます。「人の振り見て我が振り直せ」と何かにつけて昔の人はよく言いましたが、それを自分に当てはめるのは容易ではありません。
また、文章講座でよく言われていることは、
<平明>な文章 <内容>の豊かな文章 <表現>に工夫のある文章
ということです。これは井上ひさしさんの文章作成のモットーでもある
むずかしいことをやさしく やさしいことを深く 深いことを愉快に
ということで、これは文章を書くすべての人がモットーとすべきこと、とも言っています。
他界した夫もよくあちこちに原稿を書かせて頂いていましたが、軽妙な文章だと評判はよかったようです。何しろ「私には飲む・打つ・買うの三つしか道楽はありません・・・」などと書き出すのですから、読むほうはナニ、ナニと身を乗り出すわけです。また、新聞の将棋の観戦記やテレビの将棋番組の解説なども、プロが難しい専門用語を使うのは、いと容易いことで、素人に分り易く説明するほうがかえって難しいのだ、ともよく言っていました。その当時はそんなものかしらと聞いていましたが、夫の死後にある週刊誌から取材を受けました。天気予報を易しく解説することで有名になった方が、「私の師」として夫の名を挙げているというのです。その方は、その理由を問われて、テレビなどで夫の解説を聞いて「そうだ、自分もこのように易しい言葉で天気の解説をしてみようと思った」ということでした。
文章には書く人の生き方、考え方、性格、品格、知識、感性のすべてが出ると言われています。常に身を晒し、ラッキョウではありませんが一枚づつ皮を剥がれて丸裸にされていくような気がしますが、本音で書く以上これは仕方がないと覚悟しています。
|