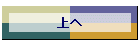
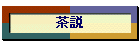
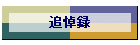


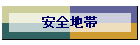

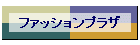
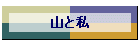


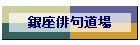
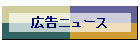
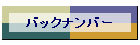
| |

東郷和彦の「東京裁判」考察
 牧念人 悠々
牧念人 悠々

外交官・東郷和彦が「歴史と外交」(講談社現代新書)の中で祖父茂徳を裁いた「東京裁判」について「祖父の戦い」とういう一章を設けて論じている。祖父茂徳は東京裁判では「禁固20年」の判決を受け、巣鴨刑務所でなくなっている(昭和25年7月23日)。当時著者の茂徳は5歳であった。父、文彦(のちの駐米大使)は外務省から終戦連絡事務局から出向して茂徳裁判の弁護活動に参画していた。東郷重徳の裁判は昭和22年12月15日から26日まで行われた。審問の焦点は東条英機内閣の外務大臣として、日本の開戦を決意したこととの関連で、真珠湾奇襲攻撃に対する責任と日本開戦自体の犯罪性の問題であった。これに対して茂徳の論理は、ハル・ノートを受けて開戦を決意したのは、自衛のために他ならないという主張であった。東条英機大将も『自衛の戦いであった』と法廷で述べている。自衛のための戦争であったという議論は、東京裁判の中核をなす「平和に対する罪」に対する真正面からの反論でもあった。ハル・ノートについて和彦は言う。「当時の日本政府がこれを事実上の最後通牒と受け止めた事は定説となっており、また。圧倒的多数の歴史家、オピニオン・リーダーは、日本政府としてはそう解釈せざるを得ない十分な理由があったと判断していると思う」。
茂徳は日米の対立の根本原因は中国における両国の権益の対立にあると考えていた。「門戸開放と機会均等」を旗印とする九ヵ国条約とスティムソン主義(米国の国務長官スティムソンは国際連盟と協力する政策を取り、門戸開放政策・不戦条約厳守を求める)の帰結として、日本の中国における権益を一挙に放棄させるのは、米国の自己権益確保のための恣意的要求にすぎず、中国における日米の権益の調整は、交渉によって、彼我の調整点を見出すほかないことを強く指摘していたのに、ハル・ノートによって、それには1.中国及び仏印からの、即時かつ無条件撤兵 2.三国同盟の条約の破棄 3.当時日本が承認していた王兆銘政権との関係断絶と蒋介石政権の承認が要求されていた。日本の和平努力が終焉した。かくて開戦となったわけである。
九ヵ国条約は大正11年、ワシントンで日本、イギリス、米国、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ポルトガル、中国の九ヵ国の間に締結された、中国の領土保全と・門戸開放・機会均等をさだめた条約である。表向きは中国の主権を尊重して国際間の紛争は話し合いで解決しようというのだが、腹は米国の権益を確保しようというものである。東京裁判で東條大将は検事団から「ハル・ノートの3原則は九ヵ国条約に含まれているのではありませんか」と問われている(保坂正康著「東京裁判の教訓」朝日選書)。日本が九ヵ国条約に違反しているというのである。
以下は茂徳の法廷での陣述である。「ハル・ノートは日本に対し、全面的に屈服か、また戦争か、ということであって、日本を戦争に追い込もうとする解釈であったわけであります。もしハル・ノートを日本が承諾するならば、日本は東亜における大国としての地位を維持できないのみならず、三流以下になることは、当時ハル・ノートを知っているもの全部の意見でありました。当時日本は、戦争か自殺かを迫られておるという感じでありました。かくのごとき情勢で自衛戦争、自衛上戦争をするのも致し方ないという考えに一致した訳であります」それに母親の言葉が添えられている。「証言の番が来た時おじいちゃまは元気だった。傍聴席から見ていてすごく、生き生きしていた」。
東郷和彦は「平和に対する罪」を追求する。「法的な正当性はなかったと思う。国際法の発展段階を考えれば、1945年の事態は言うに及ばず今日に至るまで、国際法は『侵略』は何であるかを、定義しえていない。一国が『自衛戦争』と確信して開戦した場合、これを国際法に基づいて、処断する権利は、いかなる国にも与えられていない。ましてや、戦争を行ったこと自体を個人の責任に帰してその犯罪性を追求する、国際法上の根拠は、どこにも見当たらない」。
東京裁判は勝者が敗者を裁いたものである。しかも「事後法」という虚構の上に成り立っており、米軍の占領下に行われた裁判であったことを記憶にとどめておく必要がある。このことを故意に見落とす識者が少なくないのは残念である。
|

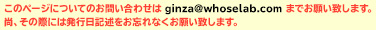
|
