百合の手紙には、男に伍して仕事をしていく女の苦悩が溢れていた。組織優先の企業社会との葛藤、個への干渉に対する苛立ち、家庭を十分にかまうことの出来ない妻の焦り、女が故に味わわなければならない性的屈辱。慶太は社会的にこの上もなく恵まれたように見える華やかなテレビの世界の女性にも深い苦しみのあることを知って、胸が痛んだ。
しかるべき教養を身につけ、望む職業に就き、男と対等に広い社会の活動に自分の生きがいを見つけたはずなのに、ふと気がつくと、自分は結婚生活というもっともな小さな社会の成功者ではないことを発見する。
女の幸せとはどういうことを意味するのだろうか。
多くの男にとって社会生活と家庭生活の両方を手にすることを考えるのは普通である。男にとって、職業という社会活動は家庭の延長線上にあって、立体的に重なり合うものではない。二つの間を水平移行すればよい。しかし女にとってはそうでない。社会活動と家庭とは大きな部分で重複する。常にどちらか一つを選択して身を置かなければならないのだ。前者を優先させれば後者にほころびが出る。後者を重んじれば、前者に後れをとる。果たして女にも男のような水平移行が可能なのだろうか。
百合については何も新たに知ることが出来ないまま、夏が過ぎ、やがて慶太の住むニューヨーク郊外の小さな町も秋の色に満たされた。
国連総会の賑わいも一段落し、ニューヨークと周辺がすっかり冬のたたずまいとなった十一月半ば、マデュカール・シャルマから手紙が届いた。
それによれば、一週間前ポカラから車で東へ三十分、シスワという町から北の方の山に入った村のヘルスポストに巡回で寄った。ヘルスポストとは、ネパールの僻地の村に設けられた簡易保健施設で、救急医療品やコンドームなどの家族計画用品が備えられ、村の保健補助員が管理している。通常の状況報告を受け、点検を終わって山を下りようとした時、正面から一人は明らかにネパール人の若い女性、もう一人は民族衣装のクルタクロワールを着ているものの、ネパール人とは様子の違う女性が話しながら上ってきた。すれ違いざま、お互いに「ナマステ」と声をかけ合ったが、マデュカールの顔を見た瞬間、その女性の顔色が変わった。
「ソノ・ジョセイハ・ダレダカ・ソウゾウデキマスカ」
マデュカールは意味ありげに問う。
「ユリデシタ。ユリ・オオヤマデシタ」
ここに来て、慶太は体中の血が頭に集まるのを感じた。
マデュカールによると、一瞬驚いた百合だが、すぐ平静さを取り戻して、こう説明した。
自分は今山間部の女性の取材に来ているが、特別な企画のために人に知られるとまずい。例えネパール人であっても、最近は日本人との接触も多いから、いつどのようにして知られるようになるか分からない。こういう理由からもマデュカールにも敢えて知らせなかった。
「ワタシモ・ジャーナリストノ・シゴトノ・セイカクハ・タショウ・ワカッテイマスノデ、ユリノ・イウトオリ・ダレニモ・ハナサナイコトヲ・ヤクソク、コマッタ・コトガ・アレバ・イツデモ・ジムショニ・レンラクスルヨウニト・イッテワカレマシタ」
そして手紙は、
「チカイ・ウチニ・マタ・ゼヒ・トレッキングニ。ヒマラヤハ・コレカラガ・サイコウデス」
と結んであった。
慶太がクリスマス休暇を利用して、百合を探しに行く決心をするのに、数秒とはかからなかった。ただちにコンピューターに向かって、百合のその後について簡単に記し、一ヵ月後のポカラ行きをマデュカールに知らせた。
十二月十一日タイ航空機からカトマンズ・トリブバン国際空港に降り立った慶太の前に広がる光景は、八ヵ月前百合と出会った時に見たものと変わるものはなかった。一つあるとすれば、ターミナルビル屋上に群がる人々の服装で、女性はサリーの上にカーデガンやショール、スカーフをしっかりとまとい、男たちはセーターやジャンパーを着ていた。
ターミナルビルに入るとき、慶太の足は思わず止まった。その場所こそ百合との出会いが始まった所だったからである。黒いティーシャツに黒いジーンズ、それにリーボックの英語名がかかとに書かれた黒のウオーキングシューズ。どことなく不安げで遠慮がちなその時の百合の姿が慶太の目に浮かんだ。
ポカラ行き最終のネパール航空便は約二十人乗りの英国製双発プロペラ機だった。澄み渡った空を背にして立つマナスルやアンナプルナ連峰、そして慶太の心の中でのヒマラヤのプリンセス、マチャプチャレもその偉容を変えることなく、南に傾いた日の光を受けて輝いていた。生あるものすべてを拒む厳冬期のヒマラヤのたたずまいは厳粛だった。
ポカラ空港ではマデュカールが、眼鏡の奥の目を光らせて待っていた。慶太は形式的な挨拶は抜きにマデュカールの手を握った。マデュカールも、自分の手紙で慶太が急きょ地球の反対側からやってくることになった事の重大さを十分に理解していた。
「とにかくホテル・ククリへ行きましょう」
四輪駆動に乗り込むと、マデュカールがすぐ本題に入ってきた。
「あなたの手紙にはびっくりしました。まさかユリがその後行方が分からなくなったなんて」
「僕にとっても、ユリがネパールに戻ったなんてまったく驚きだった。ジャーナリストは世界中飛び回るのが当たり前だから、一人の女性ジャーナリストがネパール山中を歩いたとしても、何も不思議はない。でもユリの場合はまったく別だ。ユリは自分の生き方の問題で苦しんでいる。僕がどれだけ力になれるか分からないが、とにかくユリに会って、出来ることなら励ますことだけでもしてやりたいと思っている。君には不可解かも知れないけれど・・・」
「いや私だって、何か力になれることがあれば、それだけで嬉しいです。それより特に手がかりというのは見つかっていないんですが、ユリがまだネパール中部にいることはどうやら間違いないようです」
「それはすごい。実はそれを一番知りたかった。ひょっとしてユリはもうどこか別な所へ行ってしまったのではと、そればかり気になってたんだ」
慶太はマデュカールの重大な内容の言葉に、大きな安堵を覚えた。せめてそれだけでも確認出来れば、これからの行動にも張り合いがあるというものである。
「実は一週間ほど前に、ポカラの南にタナフン郡という地区がありますが、その郡の赤十字活動の衛生ボランティアのワークショップがポカラでありました。私も家族計画やリプロダクティブ・ヘルスの問題で講師をしました。その時休憩の雑談中、ボランティアの一人が、女性の地位推進活動を計画しているノルウエーの視察グループに日本人の女性がいたというんです。それでその女性の容姿とか話し方とか聞いていると、その日本人はシスワで会った時のユリとそっくりなんです」
マデュカールは人通りの多いレイクサイド通りに曲がる時は、さすがに緊張してしばらく話すのを止め、運転に集中した。
「ユリらしいと思われる日本人の女性を見たというのは、タナフン郡のドルフェルディという村と周辺を担当しているネパール赤十字社の女性ボランティア・ワーカーです」
車はレイクサイド通りを折れると、すぐにホテル・ククリの前で止まった。このホテルもまた、四月と変わっているものは何もなかった。既に馴染みになっていた日本人のような容貌のマネジャーがにこにこしながら出て来た。
二階の部屋に荷物を置いてから、マデュカールと一緒に二階の展望用のテラス食堂に行った。午後六時を過ぎると、東京よりはるか南のポカラでもさすがにあたりは暮れてきたが、標高七千メートルのマチャプチャレは、サランコットの丘の後ろに白い清楚な姿を浮かべていた。鋭く尖った頂きには夕日が残っている。マチャプチャレ。百合はカトマンズからポカラに向かう飛行機の中からこのマチャプチャレを眺めて、そこが自分の傷ついた心を癒す場所だと悟ったのである。
マデュカールはガイド兼通訳として以前マデュカールの事務所でメッセンジャーとして働いていたウダヤという名の青年を確保してあると言った。
「ありがとう。ところで今回は全くの私事だから、出来るだけわたし一人でやれることをやってみたい。だから君に途中経過を話さないかも知れないが、どうか勘弁してもらいたい」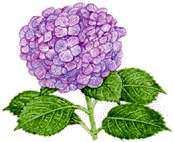
「了解です。それでは明日何時にウダヤを寄越しましょうか」
「九時半でどうだろう」
頂きを淡いピンク色に染めていたマチャプチャレも、いつのまにか濃紺のナイトガウンに着替え、やがて夜陰に消えた。
