
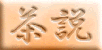

検事上がりの弁護士を「ヤメ検」という。弁護士の世界では、むしろ、尊称とは違った意味で使われている。そに検事上りが、ここ数年、大蔵省不信のあおりで、にわかに脚光を浴び、大蔵領域での起用が目立つようになった。
5年前、証券スキャンダルで発足した証券取引等監視委員会。その初代委員長に名古屋高検検事長から就任した水原敏博氏をはじめ、住専問題の預金保険機構理事長に最高検刑事部長の松田昇氏。昨年は、大蔵省指定席といわれた公正取引委員会の委員長に元法務事務次官の東京高検検事長の根来泰周氏が登用された。このほかにも、住専関係の債権管理機構や整理回収銀行などに、合せて20数人もの検事出身者が転出している。
検事の持つ「中立,厳正」のイメージが買われたのであるうが、果して効果は上がっているのだろうか。筆者の見るところ、成果をあげているのは証券取引監視委の水原委員長ぐらいしかいない。公取委の根来委員長などは、「人手が足りない」とゼネコン大阪の談合内部告発にさえ、手をつけなかった。この点に関する限り、一部新聞の批判は的を射ている。
水原氏は、東京地検特捜部の出身。60年安保時代、樺美智子さんの死因捜査を担当したこともあり、"マジメ派"の検事だった。一方、根来氏は、法務省次官当時、ゼネコン脱税で騒がれた金丸信氏との関係が取り沙汰された"属僚派"だ。公取委員長になったのも、「旧竹下派有力閣僚の推薦」と、検察部内の見方はきびしい。
証券、金融、商取引の腐敗一掃は、「時代の要請」である。検事出身の正義感と力量が求められているのに、変りばえしないのなら、"検事転用"は意味を失う。「名こそ惜しめ」という軍歌があった。「ヤメ検」とはいえ、行政機関のトップには"出自の面目"がかかっている。