|
|

寺井谷子さんの「共に歩む」を読む
『俳句は一本の鞭である』
 牧念人 悠々 牧念人 悠々

寺井谷子さんから俳誌『自鳴鐘』復刊800号を記念して出版された『共に歩む』―横山白虹・房子俳句鑑賞―(飯塚書店・平成27年5月17日第1刷発行)が送られてきた。ともに俳人であった両親への熱き思いがあふれ出ていた。「白虹・房子十二ヵ月」(第2章)で1月から12月まで各月ごとに両親の句を紹介する。「6月」白虹が「原子炉が軛となりし青岬」と詠めば房子は「原子炉の地つづきにクローバの褥」と答える。これらの句を選びぬく作業の際、谷子さんの胸中はどのようであったのかと思うと、こみ上げるものを抑えかねた。
表紙をめくった1ページ目に白虹さんの遺影とともに「俳句は一本の鞭である」の言葉が飛び込んでくる。『俳句が鞭』と私が感じたのは昨今の事である。何かにつけ俳句を頭に浮かべる。5・7・5を作ってみる。俳句が己を励ますようなところがある。横山白虹さんとの付き合いはその晩年のわずか7年半に過ぎない。しかも俳人白虹ではなく「人生の師」としてであった。
谷子さんは父・白虹について重要な指摘をされている。それは白虹さんが一高時代に創立した「一高詩会」で指導を受けた北原白秋との出会いである。九大入学前に白秋から終生の指針となる言葉を受ける。「人間死ぬときに心残りがあってはいけない。やりたいと思ってことは何でもやってみるんだ」時に白虹20歳、白秋34歳。人間はわずかな期間でも教えられた師の語った言葉が心に残る。
白虹は新興俳句運動の旗手であった。この運動は水原秋桜子が「自然の真と文芸上の真」一文を記し「ホトトギス」を離れた昭和6年を始まりとして15年の「京大俳句事件」で官憲の手により終息させられるまでの10年間の運動をいう。その代表的な句をあげる。
「頭の中で白い夏野となっている」高屋窓秋
「ラガー等のそのかちうたのみじかけれ」横山白虹
「水枕ガバリと寒い海がある」西東三鬼
「しんしんと肺碧きまで海のたび」篠原鳳作
「未亡人泣かぬと記者はまた書くか」佐々木巽
「熱い味噌汁をすすりあなたゐない」波止景夫
「戦争が廊下の奥に立ってゐた」渡辺白泉
この本を読んで羨ましいと思うは谷子さんの場合、母の胎内にいる時から「俳句」があったことである。さらに4歳の時には戦争中休刊していた『自鳴鐘』が復刊、5・7・5がそこらじゆうに散らばっていた。音として『俳句』が耳から入ってきた。私など俳句は「目」から入ってくる。「耳」と「目」とでは大違いである。つまり、谷子さんは「言葉の波音」が自然と分かる人である。その谷子さんが「言葉」というものへの親しさや尊敬があれば「俳句」がずっと身近になってくるという教えを重く受け止めよう。
「月光を父の後ろに居て浴びる」谷子
「昨日来て今日来て母の庭の梅」谷子
|

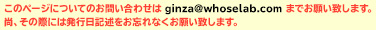
|
