
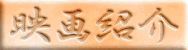
 | 大竹 洋子 |
| 原作・監督 | 山田洋次 |
| 製作 | 山田洋次、朝間義隆 |
| 撮影 | 長沼六男 |
| 美術 | 出川三男 |
| 音楽 | 山本直純 |
| 出演 | 西田敏行、小泉今日子、吉岡秀隆、 田中邦衛、倍賞千恵子、松坂慶子ほか |
渥美清さんが亡くなって、“寅さんシリーズ”が消えてしまった。そして登場したのが「虹をつかむ男」である。1997年のお正月作品として作られた「虹をつかむ男」は、当時はまだシリーズ化が決っておらず、渥美さんの追悼を色濃く打ち出したものだった。だが、2作目の「南国奮斗篇」は、観客にシリーズ化を予感させ、次はどうなるかを期待させる作り方になっている。営業不振の地方の映画館主、銀(しろがね)活男を主人公に、映画への愛をつづる喜劇の王様、山田洋次監督新シリーズの誕生である。
活ちゃんと呼ばれる銀活男は西田敏行、活ちゃんを手伝う若者、亮は吉岡秀隆、寅さんの甥の満男クンを演じた俳優である。この吉岡秀隆が、寅さんと活ちゃんをつなぐ懸け橋となる。そして、彼が伯父さんだったフーテンの寅さんの二代目であることを、観客は確認するのである。
亮は大学を卒業して電気店に就職したが、どうも仕事に身が入らない。そんなある日、1年前にアルバイトをしたことのある徳島の映画館、オデオン座館主の活ちゃんが上京、ひょんなことから活ちゃんに再会した亮は、会社を退職、活ちゃんを追って家を出る。オデオン座を一時閉館して今は巡回上映の旅に出ている活ちゃんは、紺碧の海が輝く奄美大島の砂浜にいた――。
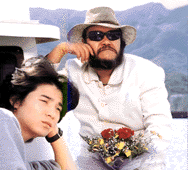
家をあとにする兄を心配する妹、下町で工務店を経営する人の善い両親、新しい配役による新しいファミリーの出現である。寅さんの妹で、満男の母だったサクラ役の倍賞千恵子は、亮が好きになる子持の若い女性、節子の叔母役で出演する。
映画を大衆のものとはっきり捉え、作家のひとりよがりを警戒する山田洋次さんにとって、1作目の「虹をつかむ男」は、映画マニアを意識しすぎたという反省があった。活ちゃんが往年の名画として次々に上映してみせた「かくも長き不在」「雨に歌えば」「禁じられた遊び」「ニュー・シネマ・パラダイス」「東京物語」などに代って、今回は「雪国」と「風の谷のナウシカ」の2本だけが起用される。南の島の人々がみる雪国の景色と、環境問題としてのナウシカ、山田さんらしい気配りである。
マドンナ役は松坂慶子と小泉今日子。南国を舞台にしたこと、それにふさわしいラテン音楽を使用したことが、この作品の特徴であり、何よりすばらしい点である。作品がぐっと明るく、陽気になった。
小さな島の公会堂で映写機がこわれてしまい、なかなか上映が始まらないのに騒ぎはじめた観客をなだめようと、活ちゃんがやおら歌うのがデーオ、デーーオ、「バナナ・ボート」である。つづいて小泉今日子が加わって「キサス・キサス・キサス」。すっかり調子に乗った村人たちは全員で踊り出す。私はこのシーンに一番感動した。あとは笑いっぱなしである。とにかく山田さんはうまいと思う。
小泉今日子が演じるのは、ミュージシアンに憧れて上京し、幼い男の子を連れて島に帰ってくるバツイチの女性、節子である。彼女を黙って見守る両親、可愛いがために妹につらくあたる乱暴者の兄。これは室生犀星の『あにいもうと』の設定である。

もう一方のマドンナ、松坂慶子は活ちゃんのかつての恋人で、今は夫が留守がちの二児の母の松江。活ちゃんと旧交を暖めるが、島の女を捨てる気はない。その松江に会おうと、活ちゃんが白いスーツに身をつつみ、花束をもってやってくる。
吉岡秀隆は、なんだか頼りないが筋だけは通したい都会の若者を見事に演じる。亮が活ちゃんと並んでこの作品の二本柱であることは間違いなく、山田洋次さんの秘蔵っ子ぶりは遺憾なく発揮される。そして主役の活ちゃんの西田敏行。やはり山田さんのお気に入りの俳優で、映画への情熱もだしがたい人物に最適任なことは確かである。
しかし、敢えていうなら、彼は時にむさくるしすぎるのではないだろうか。特によくないのはポスターの彼である。ヒゲ面にオレンジと黄色のアロハシャツで蛇味線をかかえているが、この図柄をみて、映画をみたくなくなる人がきっといるのではないかと思うのだ。一方、白いスーツにサングラスの活ちゃんは、まるでハンフリー・ボガードのように気取っている。
映画は私たち観客の夢である。どうぞ活ちゃんをもう少しきれいにしてください、というのが、このシリーズを愛し期待する私の心からのお願いである。毛糸の腹巻をしていても、寅さんはあのようにダンディーだったではないか。
