
鹿沼市立 川上澄生美術館
 小さな個人美術館の旅(5)
小さな個人美術館の旅(5)星 瑠璃子(エッセイスト)
初夏の風に誘われて電車に乗った。窓外の田園に早苗が光って微かにゆれている。宇都宮からJR日光線で十五分。鹿沼の駅で十人くらいの人が下りた。駅前の大きな楠の木を見上げていると、どこへ行ってしまったのか、人々の姿がいつのまにか消えている。上り下りあわせて一時間に二本しか列車が通らない駅前広場はしんと静まりかえって、明るい空が、からりとひろがっているばかり。そこからまっすぐに歩いて十分。黒川までくると、対岸に緑のとんがり屋根が見えた。川上澄生美術館だ。

鹿沼は木材の町という。そこに木版画家・川上澄生の美術館ができたのは、「木」の縁ばかりではない。鹿沼市出身のコレクター長谷川勝三郎氏(現名誉館長)が澄生の教え子だった。戦時も守りぬいた作品二千点を寄贈、これをもとに、平成四年、美術評論家小林利延氏を館長に迎えて市立美術館が開館したのである。
ここでは常設展というものは行わず、年に二回、企画展を開く。いまは「蔵書票の川上澄生」を開催中だが、一階のオープンスペースには竹久夢二、恩地孝四郎ら日本の版画家のほかヨーロッパの作家の蔵書票も集め、カタログは百六十ページを越える充実ぶりだ。
ぷんと木の香りのする明治の洋館ふうの幅広の階段をゆったり上ると、正面に、かの有名な「初夏の風」。この作品だけは企画展のテーマに間係なぐ、毎年この季節がくると展示するという。

|
かぜとなりたや はつなつのかぜとなりたや かのひとのまへにはだかり かのひとのうしろよりふく はつなつの はつなつの かぜとなりたや |
川上澄生は1895年の横浜生まれ。三歳で東京に移り、青山師範付属小学校から青山学院中等部、高等部と進んだ。クラスメートとコーラスグループをつくり、セカンド・テナーで活躍するなど明るい学生生活を送っていたが、二十歳の時、母の死にあう。一力月も学校を休んだという落ちこみようだった。翌年、高等部を卒業すると、再婚した父の家を出てアメリカからアラスカを放浪の旅。アラスカでは鮭缶詰製造人夫などをやって、帰国した。二十六歳で栃木県立宇都宮中学校の英語教師となり、一度は退職するが、疎開先の北海道から戻って今度は県立宇都宮女子高等学校の教師に。以後ずっと宇都宮に住んだ。
大好きで、「ひそかに師と思っているくらい」だったフランスの画家アンリ・ルソーは税官吏。「師弟」ともに「日曜画家」というわけで、澄生は毎日学校へ行き、タ方から日が暮れるまでは野球部の副部長としてノックのバットをにぎり、夜になると詩を書き、こつこつと版木を刻んだ。
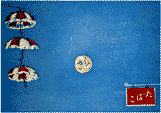
|
海の向ふの明るい風景の中に 黒い衣を着た女が 自堕落に ねそべつている ああ 恋人よ 手を延ばしても届かない 幻想の恋人よ |

住 所 栃木県鹿沼市睦町287−14 TEL:0289ー62ー8272 交 通 JR日光線鹿沼下車徒歩10分 又は 東武日光線新鹿沼下車徒歩20分 休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

星 瑠璃子(ほし・るりこ)
東京生まれ。日本女子大学文学部国文学科卒業後,河出書房を経て,学習研究社入社。文芸誌「フェミナ」編集長など文学、美術分野で活躍。93年独立してワークショップR&Rを主宰し執筆活動を始める。著書に『桜楓の百人』など。
