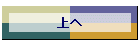
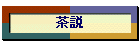
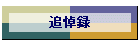


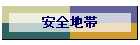

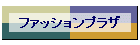
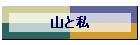


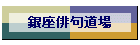
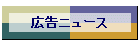
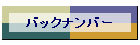
| |

大東亜戦争とは何だったのか
 牧念人 悠々 牧念人 悠々

偕行社・軍事史学会・日本危機管理学会主催のシンポジウム「大東亜戦争とは何だったのか」を聞く(国士舘大学梅が丘校舎34号館)。初めに波多野澄雄筑波大学大学院教授の基調講演があった。『開戦史研究の現段階』をテーマにして話をされた。頂いた文献資料が貴重であった。真珠湾謀略説に関する書籍だけで15冊を数え、開戦史を含めると60冊を超える。今後の勉強の参考資料になる。波多野教授の話では「日英戦争」としての大東亜戦争を捉える必要があるのではないかと言う指摘は目新しかった。教授は「大東亜戦争」でも「太平洋戦争」でも名称はどちらでもよいとされたが、昭和16年12月12日閣議決定された「大東亜戦争」を支持し、この名称にこだわりたい。開戦史についは雑誌「偕行」(昨年12月号)に掲載された永江太郎さん(陸自59)「米国資料から見た開戦経緯」が私にはわかりやすかった。とりわけ「開戦の責任の視点で見ると開戦を望んでいたのは明らかに米国であり、それもルーズベルト政権であった」と明快であった。この論文は一読に値する。
池田十吾国士舘大学大学院教授は「日米交渉におけるアメリカの態度」について話をされた。日米交渉は「呪われたものであった」と重光葵の言葉を引用された。この言葉は重光の著書「昭和の動乱」(下巻・中央公論社)にある。「日米交渉なるものは分裂した外交によって行われた。その結果は初めより呪われたものである」という。紛争を戦わずしてまとめ上げるのが外交官であってみれば当然の感慨であろう。私はむしろこの著書の書き出しに記した重光の文章が忘れ難い。「日本人は健忘症である。第一次近衛内閣が何をしたのか、また日本人のために如何なる存在であったのかは、さらりと忘れてしまっている。日本人の政治的責任感は遺憾ながら一般的に薄い」とある。第一次近衛内閣は昭和12年6月4日、組閣したが、その直後の7月7日盧溝橋で日中両軍が衝突、日中戦争が起こる。11月6日日独伊防共協定調印、昭和12年12月13日南京陥落、昭和13年1月16日「国民政府を相手にせず」の近衛声明を出す。蒋介石を中心とする民族統一の力を正しく見なかったとして不評であった。戦争長期化の一因ともなった、昭和14年1月4日総辞職する。なるほどと思う。日米戦争の近因である日中戦争、三国同盟などが起きている。重光が「日本人は健忘症である」と言うのは重光の怒りでもあった。池田教授の話は聞くべきものが多かった。
山崎志郎首都大学東京大学院教授の話は「昭和16年の物資動員計画と開戦判断」であった。とりわけ戦略物資の輸入計画、需給対照と補填計画、鋼材配当案の推移、主要物資供給力等の資料が表としてまとめられてあるのが参考になった。
「開戦による1942年度供給力の追加見通し」の表では「11月開戦」と「3月開戦」で比較すると、開戦を4ヶ月のばすと、ニッケル、普通・高級アルミ,錫電気銅、マニラ麻、生ゴム、タンニン材料、ひまし油、キナ皮、トウモロコシなどが半減している。原油は変わらない(206000kl)。勝負を短期決戦とすれば開戦時期は早ければ早いほどよいという数字であった。
森山優静岡県立大学準教授の「開戦決意の根拠」「当時の指導者はなぜ判断を誤ったのか」などの話を聞きながら「大東亜戦争は何だったのか」を考えた。私の頭の中には杉之尾宜生まれさん(陸自61)が前掲の『偕行』(昨年の12号)に書いた「大東亜戦争開戦経緯・聖軍関係」がへばりついて離れない。この論文の最後に「“日米避戦は成就出来たであろうか”と自問すると答えは“否”である」とあり、さらに「米大統領ルーズベルトは昭和15・16年の早い時期に“日本は武力を以て屈服させる“と決断していた」と記す。だからアメリカは「太平洋戦争」と限定した言い方をする。日本は国力を伸長しながらアジア諸国との共存を考えて「大東亜戦争」と名付ける。戦後独立したアジアの国々は日本に感謝している。「なぜ日本は中国に謝罪ばかりを繰り返すのか」と疑問さえ投げかけている。
日本は狡猾なアメリカに仕向けられた戦争に引きずり込まれ、敗戦の憂き目を見たというわけである。東京裁判で東條英機大将が証言した「大東亜戦争は自衛戦争である。敗戦の責任は私にすべてある」は正しい。だが、「戦争には負けたらだめだ」ということでもある。「兵を養うは百年の計」と言われる所以である。今後も自衛戦争の可能性はある。大東亜戦争70周年を迎えた今こそ国政の最下位に位置付けた防衛政策を最優先に引き上げなければこの国の明日はないと痛感する。
|

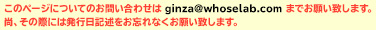
|
